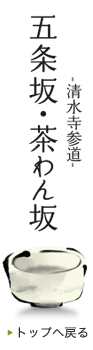陶芸の世界の革命者たち「走泥社」
「走泥社」は八木一夫さん、鈴木治さん、山田光さんといった方を中心に、京都在住の陶芸家の同志的な集まりとして、1948年に発足しました。一番多いときは30人余りのメンバーがいました。ちょうど半世紀にあたる1998年に解散となりましたが、陶芸、芸術の歴史の上で一時代を築いた、ということになるでしょうね。
「走泥社」が生まれた当時はまだ戦争が終わった直後。それまで、とりわけ戦時中はあれやったらいかん、これやったらいかん、って窒息状態のような世の中でしたから、一気に重石が取れたような状況でした。同時にヨーロッパなどから新しい芸術の動きがたくさん日本に入ってきた。「走泥社」ができたことには、そんな社会状況も影響していたと思います。
「走泥社」が生み出したものの代名詞はオブジェですが、簡単に言うとこれは「壺の口を塞いだもの」を作品とすることです。創立者の一人である鈴木さんが述懐していますが、「当初”壺の口を塞ぐ”ことがそんなにすごいことは考えていなかったが、後から思えば本当に大事業だった」といいます。現在ではオブジェは当たり前のように陶芸の作品として作られていますし、むしろ展覧会じゃ通常の器以上に幅を利かせていたりもしますが、当時は本当に革命的なことだったんですよ。
オブジェなど新しい芸術作品を作る動きは、日本だけじゃなくてアメリカやイタリアなど世界的にもほぼ同じ時期に起きたものだったようです。戦争が終わった、ということがもたらした空気の変化が、世界中にあったのでしょうね。
走泥社は年に東京、京都で展覧会をやることは決まっていましたが、特にきつい縛りはありませんでした。組織としてはゆるゆるとしていて、意識としてはもう個人がそれぞれで、思い思いに作品を作っている感じでしたね。
私自身が加入したことにはそこまでものすごく大きな理由があったわけではないんです(苦笑)もともと私は彫刻を学んでいて、今もある二期会という公募展に参加していました。一方でその頃は走泥社も同じ会場で展覧会をしていて、八木(一夫)さんもご近所でしたから父(二代目林紅村)とも交流があって、親しくしていたんですよ。そんな時、たまたま私が二期会に作品を出さなかった時期があったんです。それを知った八木さんから声をかけられて、走泥社に入ることになったんです。別に私自身はたまたまその時作品を出すのをやめただけだったんですが、どうやら八木さんは私が本当に彫刻をやめてしまったと思われたようで…ある意味、運命の悪戯のようでしたね(笑)
まあ、実家が家業で陶芸をしていましたし、土は身近な存在でした。時折手伝いもしていましたね。でも正式に学校で技術を教わったわけではなかったですし、焼物を生業とするつもりではなかったんです。それでもこの道に進んでしまうのは、この五条坂・ちゃわん坂という地域ならではの面白さかもしれませんね。

林秀行(はやし・ひでゆき)
1937年京都生まれ。京都市芸術大学彫刻科卒。林家の長男(弟は三代目・林紅村)。
1964年に走泥社の同人となり(98年の解散まで所属)以来、現代陶芸作品の牽引者の一人として活動。前衛的な陶芸美術作品、オブジェ作品を数多く制作してきた。
日本国内はもちろん、ロサンゼルス、パリ、ジュネーブなど海外でも数多く展覧会を開催・作品を発表している。2004年には第17回京都美術文化賞を受賞した。
現在は京都造形芸術大学客員教授。
▶ 走泥社公式Webサイト

ものをつくる過程はまっすぐではない。合理性とは逆のところにいる。
だからこそ、面白いものができるんです。
私がオブジェ作品を作るようになったのは、30歳くらいのときです。几帳面に、定規で図面を引いてから作っていたような仕事が、近頃は特別にこれ、といって囚われてものを作ることはなくなりました。土に触れているうちに思い浮かんだ形を作っています。若いときは難しいものにしなきゃいかん、とか頭で考えていたんですが、今は学校で教える際も「手で考える」ように言っています。結局、ものは「手」で作っていますからね。あとは心の問題でしょう。大体のイメージはありますが、きっちり最初から設計図があるわけではない。とにかく手を動かして、道草をしたり寄り道したり、右往左往しながら、ゴールにたどり着くんです。その過程が、まっすぐにいかないのが面白いんですよ。
今の世の中って何事も真っ直ぐ、効率や合理性ばかり求めるでしょう。我々の仕事は逆で、不合理なんです。もちろん商売として考えたらそれだけではいけないけれど、効率が良ければいいものができるわけではないし、合理性とは逆の方向にいる。だからこそ、面白いものができると思うんです。

もっと「職人」という存在や仕事の価値を、世間が認めなければならないと思います。
同じような焼き物でも、人間国宝の陶芸家が作ったら何千、何万と値段がつくものが、職人さんが作ると何百円とかで売られたりする。それを見た人が、職人より「陶芸家」の方がすごいんじゃないか、と思ってしまう。でも、元々美術とか工芸とかはわかれていなかったんですから。昔からの職人さんがやってきた仕事があるからこそ今があるわけですし、結局世の中の仕組みの問題なんですよね。むしろ私たちの親の世代の職人さんと今の作家を比べたら、正直技術は前の世代の職人の方がずっと上だと思いますよ。使ってる道具や便利なものは今はいろいろ揃っていますが、それで何とか補っているようなものです。その分、先人の培ってきた技術とかは失われつつある。陶芸だけじゃなく、伝統工芸全体にその傾向がありますね。
もっと、職人という職種やその仕事を、世間がもっと認めなければならないと思います。
極端にいえば、作務衣を着て、仙人みたいな雰囲気を漂わせて、神秘的な感じが出ていて…そういう姿でも見せて、陶芸家ってすごい!もちろんこれは冗談ですが(笑)職人という存在の価値を、もっと多くの人に知ってもらう必要があることは確かです。

焼き物は日本の文化と密接に関わる存在。それに携わる者の責任は重大です。
焼き物というのは、毎日の生活に密着した存在です。三度の食事の際には焼き物の器が出てくる。特に日本は外国に比べてずっと、生活における焼き物の関わりは深い。土やら磁器やら、無地に染付け、色絵と、種々雑多な陶磁器が一般家庭の食器棚に揃っている。そんな国は世界的に見ても日本くらいでしょう。日本は大きさも形も個性豊かで本当に多彩です。おそらく風土の影響なのでしょうが、それでも一般の人がこれだけ日常の中で焼き物に触れ、こだわりを持っていることは日本特有の文化の一つだと思います。雑多で色々なものがある中に美を見るのも、日本らしいところでしょうね。
京都や京焼も同じで、本当に色々なものがあります。この五条坂・ちゃわん坂も、無地の器を作る人から、私のようにオブジェを作る人まで、さまざまな人間がいます。文化の多様性がここにある。世界に冠たる焼き物文化の聖地、それが京都だと思いますよ。今は状況が変わっているところもありますから一概には言えませんが、明治維新のころ多くの人が渡欧して学ぶことで箔をつけたように、京都で焼き物を学ぶことは一種のステータスになっていたんです。また、先ほどお話しましたが、焼き物は一国の食文化にも密接に関わっている。文明の生活文化の根幹を成す存在のひとつとも言えると思います。その分、我々焼き物に携わっている者は責任重大です。なんたって、文化の片棒を担いでいるわけですからね。ちょっと偉そうな言い方ですが、一人一人がそれぞれの立場でがんばる、そう思います。

文化で成り立ってきた場所だからこそ、
文化的なものを生かして日々の糧を得るべきだと思います。
焼き物の文化を支え携わる人はたくさんいる。それを生かさない手はないでしょう。
焼きもの本来の在り方を今一度問い直し、それに関わる一人一人がなすべきことをするべきだと思うんです。
この地域はもちろん、京都自体、文化を生かすことで、成り立ってきた街なんですからね。