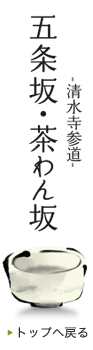- 清水寺参道 五条坂・茶わん坂
- 作家・店舗紹介
- 清水六兵衞
清水六兵衞
清水六兵衞家は、江戸時代中期から230年以上続く、京都を代表する陶工の名跡。その跡取として1954年に生まれる。父は7代清水六兵衞(彫刻家・清水九兵衞)。襲名前の名は柾博。早稲田大学理工学部建築学科卒。その後京都に戻り研修、本格的作陶に入る。研修中の頃よりグループ展に多数参加、80年代より公募展などでも受賞を重ねる。作風は幾何学的な作品形状に、焼成時の形の変化を融合させたもので、釉薬の効果とも呼応し独特の作品を生み出している。2000年に清水六兵衞を襲名。旧来の伝統を踏まえつつも、現代の感覚を生かし、新たな作品の制作に日々取り組んでいる。 現在は京都造形芸術大学教授も勤める。
清水の地で8代に渡り続いてきた陶芸の名家・清水六兵衞家。
歴史と伝統と共に歩みつつも、常に新しいものを生み出し続けているその姿勢は、バラエティ豊かな清水焼の存在そのものにも重なります。歴史の重みある名前を背負いつつ、新しい自分の表現を希求し続けているご当代・清水六兵衞さんにお話をお伺いしました。
歴史を背負いながら、各代が個性を発揮する「清水六兵衞」
インタビュアー(以下I)>
ご当代は8代目(清水六兵衞)でいらっしゃいましたね。初代から数えると何年くらいになるのでしょうか。
清水六兵衞先生(以下R)>
初代・清水六兵衞はちょうど今の大阪・高槻あたりの出です。
その後五条坂へ出てきて修行し、「清水」の姓を名乗るようになったのは1771年。それから考えると、現在までで240年ぐらい続いてきたことになりますね。
この部屋(※)にある作品はほんの一部です。初代から四代目くらいまでの作品はあまり残っていません。五代以降のものは結構残っていましたが資料館や美術館に寄贈したものもあります。
※ インタビューはご自宅の二階、作品展示室にて行いました
――I>
こちらに置かれている作品は歴代ごとに並べられていますが、それぞれ個性や特徴がとても出ていて作風が違っていますね。磁器の染付けもあれば、色絵だったり…茶道具に壺にオブジェに…作風も方法も全然違っています。
――R>
その辺が不思議なところなんですよね。
各代が先代とは同じことをやらずに、それぞれ独自のものを作ってきたんです。
作品に入れる「銘」も…うちは代々六角の中に「清」の字が書かれてるんですけど、この字が各代で違います。
三代から五代は磁器の洋食器なども作っています。
五代は結構新しいことをやっていたようで、七宝の技法を応用した「音羽焼」と呼ばせたもの。時代的にもアール・ヌーヴォーが入ってきたころだったので その影響もありますね。
かと思えば、(野々村)仁清風のもあったり、青磁や天目なんかもあって、本当に色々です。なんでもありですね。
六代は若いころは彫刻風の作品も作っていましたし、唐三彩の研究もしていました。他にも赤三島と名づけた器などもあります。
ところで、六代目は先代の五代目が使っていた釉薬を使わなかったんですよ。
五代目のころはいろんな釉薬があったんですけどね。河井寛次郎さんも、若い頃に釉薬顧問という形でうちに出入りされていたということです。 元々、寛次郎さんのところの窯(現在の河井寛次郎記念館の登り窯)は五代目が持っていたものらしいんですよ。それを後に寛次郎さんに譲ったということです。
その頃にはいろんな釉薬を研究してたんですけれど、六代目がそれをほとんど使わなくて終わってしまったのは残念ですよね(笑)
父(七代目)は陶芸というよりは彫刻家(清水九兵衞 ※)としての活動の方が長かったんです。40歳過ぎてから一度やきものをやめて、それから20年程、金属彫刻家としてやっていました。京都駅とかみやこめっせ(京都市勧業館)の前にある赤い彫刻は父の作品で、他にも全国各地にあります。
――I>
お父様(7代目)の作品は六兵衞を襲名された後のやきもの作品も、土というよりは金属的で面白いですね。
ご当代の作品も、とても現代的なデザインで…正直驚きました。
――R>
始めはろくろを勉強して、その後釉薬を1年勉強しましたが、今は土を板状にのばして作る「タタラ成形」という技法を主に使っています。
大学では建築を学んでいたので…作品を作る前には図面を引きます。それをもとに各面の型紙をつくり、それに合わせて切り取った土の板を貼り合わせて形をつくります。
――I>
本当に各代で作風が全然違うんですね!
代々お名前を継承するようなお家だと、同じような作風を受け継ぐイメージがあったのでとても驚きました。
――R>
まあ、ちょっとうちの場合は極端すぎるところもあるかもしれませんが(笑)
――I>
特に先代やご当代の作品は現代アートのオブジェといった感じで、私はかえってとても新鮮に感じました。
しかし、「清水六兵衞」の名を聞くと、「京都らしい」「清水焼・京焼らしい」というイメージは持たれるものだと思うのですが、そちらに対してはどのようにお考えをお持ちでしょうか。
――R>
特に京焼を意識して作っているわけではないのですが、京都の作家って、ほかの地域の作家とは何か違う。デザイン性なのかイメージなのか…
あまり「土味」を全面に出したようなものは出てこない。そういう意味では、京都のものは端整というか、非常に洗練されていますよね。それがひとつの特徴なのかもしれません。
まあ、京焼ってほんとに「これだという特徴がないのが特徴」みたいなものなので、正直「なんでもあり」なんです。
私が作りはじめたのはオブジェで、彫刻的な造形に取り組んできたんですけど、同じ手法で「器」にもっていったらどうなるのか…これが八代を継いでからのひとつの方向性かもしれません。
実は名前を継ぐまでは器ってあまり作ってないんですよ。意識するようになったのは「六兵衞」になってからです。
「清水六兵衞」の各代は、その生きた時代の中で割と先のところをずっと歩み続けてきたのかもしれないな、という気はしますね。実際、自分もその流れに乗っているような感じがします。
自分の代の特徴を出さなきゃいけない、先代と同じはだめ、という暗黙の了解…プレッシャーがかかっているところはあります(笑)
――I>
八代目・清水六兵衞はこんな新しいものを作っている!というのは清水の地域にとっても大きなアピールになるでしょうね。しかも歴史ある家から新しい感覚の ものが生まれているというのは、非常にインパクトがあると思います。古いものの中から新しいものが生まれるのも、京都らしさのひとつかもしれませんね。




様々な芸術家との交流できる環境があった


――I>
先ほど河井寛次郎さんのお名前を挙げられていらっしゃいましたが、清水六兵衞の家では様々な作家や芸術家との交流…「コラボレーション」をされていたそうですね。
――R>
四代から五代にかけて、「遊陶園」という浅井忠(※2)が主体となって指導していた陶芸の研究団体がありました。浅井忠は洋画家ですが、アール・ヌーヴォーの影響を受けたデザインなどがあり、それらのデザインを元に六兵衞が作ったりしていました。このような活動はそのあと、神坂雪佳(※3)が主導した「佳美会」という研究会に引き継がれていきます。
※2 浅井忠(あさい・ちゅう):日本の洋画壇の萌芽期を牽引した洋画家。フランス留学後、京都に移り住み、美術学校で教鞭をとる傍らでデザイン研究を行った。
※3 神坂雪佳(かみさか・せっか):明治~大正に活躍した日本画家で図案家。特に琳派に傾倒し、陶芸や漆器・染織品などに工芸図案の提供も積極的に行った。浅井没後の京都のデザイン界を支えた人物。
――I>
神坂雪佳デザインのお皿は、現在も細見美術館で販売されていらっしゃいますね。では、「作家」さんというのは基本的に全ての工程をやる方のことをいうのですね。
――R>
「水の図」の向付ですね。オリジナルは四代、五代目が神坂雪佳の図案をもとに作ったものです。この下図は今もうちに残っているんですよ。それをうちの工房で復刻して作っています。
昔は、陶芸家も画家と交流したり、日本画家に弟子入りして絵を習ってたりしていたようですね。
日本画の師匠だった幸野楳嶺や、竹内栖鳳、富岡鉄斎、横山大観、橋本関雪らとの合作も存在しています。
――I>
日本を代表する日本画家ばかり!凄い人のお名前が次々と出てきますね。それだけ様々な方と交流があったんですね。
――R>
ちょうどそういう人たちが近くに住んでいたということもあったからかもしれません。
谷口香嶠さん(※4)なんかは実際にうちの2階に住んでいたそうで、時々部屋から出てきては何かしら描いて、また部屋に戻る、みたいなこともあったようです。他にも、交流のあった芸術家や作家が三代目に贈った寄せ書きなんかも残っています。
※2 谷口香嶠(たにぐち・こうきょう):明治~大正期の日本画家。幸野楳嶺の門下生で、竹内栖鳳らと共に楳嶺門の四天王とも呼ばれる。特に歴史画に優れた作品を残している。
もう少しさかのぼると、江戸時代、初代が活動していたころは東山七条の妙法院というお寺が一種の文化サロン的な役割を果たしていました。そこへは円山応挙なんかも出入りしていたそうで、初代が形を作って応挙が絵を描いたと伝えられている水指が残っています。
昔はそういう、サロンみたいに色々な分野の人との関われるところがあったんですが、今はそういうのがなくなってしまいましたね。
――I>
今は結構自分のアトリエに閉じこもってきちんと描こうとする人が多いのでしょうね。昔は「描いて!」といわれればその場でさらさらと描く、なんて人もいたようですが。
ご当代ご自身ではいかがでしょうか?
――R>
以前、洋画家の黒田克正さんとコラボをやったことがあります。実はまた何かしましょう、という話もあります。
陶器の町・清水自体を学べる場所を
――I>
展示室はご自宅の建物を利用されているそうですが、先生は、ずっとこちらにお住まいだったのですか?
――R>
そうですね。昔と比べるとだいぶ改装していますが、ここで生まれ育ちました。
実は元々、ここは料理屋さんだったんです。六代目がここに移ってきたのは戦時中です。京都が空襲にあうかもしれないということで、火災対策のための道路拡幅で立ち退きに遭い、当時空き家になっていた今のところに移ったそうです。
――II>
なるほど、戦争の影響があったのですね。五条通も戦争の影響で拡張されていまのような大きな道路になったとは聞いていましたが、そのことがあったのですね。
――R>
昭和35年頃まではここにあった登り窯を使っていました。昔はこの辺は沢山の登り窯があったそうですが…
でも登り窯は本当に炎が間近で感じられますね。私が勤めている大学(京都造形芸大)には穴窯があってそこで数点焼いたことがあります。当然ですが、電気窯とは違うやきものができますね。
――I>
昔は職人さんが沢山集まっていたこともあって、五条坂の周辺は共同で使う登り窯の煙が沢山立ち上っていたと聞きます。おかげで煙だらけで…洗濯物も干せなくて、たんすの中まですすが入っていたとか。
――R>
その当時は、それが当たり前だったんですよね。今もいろんなやきものに携わっている人たちがここの地域にいるということがすごく大事なことだと思います。
そして、それをアピールすることが大事だと思います。
――I>この先、五条坂やちゃわん坂の地域の今後は、どのようになってほしいとお考えですか?
――R>
京都市内の真ん中って、ずい分変わってきているじゃないですか、町家をレストランにしたりとか、ブティックにしたりとか。
五条坂も、もっと、やきものを見にきてもらえるような町にしたいですね。
そのためには、京焼の美術館とかは必要だと思うんですけどね。河井寛次郎記念館や近藤悠三記念館、清水保孝さんのところのギャラリー、うちのギャラリー六兵衛もあるのですが。
――I>
施設・スポットはあるんですよね。そこにつながりがあればよいのかもしれませんね。
――R>
その点ではこの五条通は問題ですね。南側と北側の街が広い道路で分断されてしまってますから。
この地域は繁華街も近いし、飲んでも歩いて帰れる(笑)山も近いし、ちょっと歩けば自然に会えるところもいいですね。ただ、観光シーズンともなると、細い道に観光バスや車がいっぱいになるので、移動が本当に大変です。
電柱をなくすだけでもいいから、道を変えれば、人の意識もずいぶん変わると思いますよ。
――I>
ご当代としては、具体的に何か活動をされたことはおありですか?
――R>
工房のギャラリーと、ショップをきれいしたことでしょうか。ギャラリーは昔の蔵を利用しているのですが、三ヶ月に一回くらいのスパンで展示替えをしていく予定です。
あとは、自宅二階の展示品を公開できたらいいなあと思っているんですけどね。
いつ実現できるかわからないけれど、歴代の作品をどこかで展示できる方法を探したいと思っています。それが自宅なのか、工房の方に持ってくるかはわかりませんけれど。
――I>
清水六兵衞歴代、となると、五条坂やちゃわん坂、清水の地域を概観できる場所にもなりそうですね。やはり「最古参」にあたる家、という意味もありますでしょうか。
――R>
そうですね、昔からこの地でやきものを作っていて、それをずっと続けていくことも意味があることだと思います。