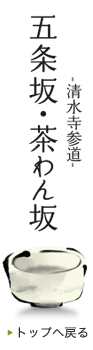- 清水寺参道 五条坂・茶わん坂
- 作家・店舗紹介
- 澤村陶哉
澤村陶哉
1947年生まれ。「鉄釉陶器」で人間国宝に認定された陶芸家・清水卯一を父に持つ。龍谷大学文学部史学科卒業後、父に師事し作陶を学ぶ。第19回日本伝統工芸展(1972)に初入選、以後各公募展にて入選を重ねる。1999年には「鉄絵亀遊文掛分扁壷」が駐日フランス大使館に収蔵されるなど、海外でも高い評価を受ける。2002年より日本工芸会理事。 2005年には作陶35年展を高島屋(京都・名古屋・大阪)にて開催した。父から受け継いだ五条坂にある工房はギャラリーも兼ね、一般に公開も行っている(無料)。
かつて数多く清水周辺にあった登り窯は、現在はほとんど姿を消してしまいました。
その登り窯での作品製作に現在もこだわり、自ら登り窯を築き創作活動を行っているのが、三代目・澤村陶哉さんです。
失われつつある文化を大切に受け継ぎ、そこから新しい作品を生み出している澤村さんに、伝統の窯へのこだわりと清水の地域への思いをお伺いしました。
自然に進んでいった「ものづくり」への道―父、祖父の姿勢から学ぶ
インタビュアー(以下I)>
澤村先生は生まれも育ちも「茶わん坂」とのことですが…何か思い出などはおありですか?
澤村陶哉先生(以下S)>
そうですね…何回か舗装を繰り返してるんですが、昔はこのあたりはコンクリートに砂利が混ぜてあるようながたがたした道のときもありましたしね。だから、そういう(清水寺への)「参道」としての道だったのと…上に車止めがされているところがあってもう少しこう風情があったんですが今はもう、両サイドから車が来るようになってしまって…そういう移り変わりは見てきていますね。
――I>
先生は三代目ということですが、早いうちから跡を継ごうとか、焼き物の道にとは思っていらっしゃったのですか?
――S>
ごく自然にそうでしたね…結構同じような立場で抵抗感があったという方もいると聞きますけれど、私はそういうことはなかったですね。まあ、親の育て方もあったんでしょうけど、さほど抵抗もなく自然に同じ道に進みましたね。
父もそういうことを口にするような人でもありませんでした。まあ、後から周りに聞いてみると、内心は跡を継いで欲しいという希望は持っていたようですが、個人的に強制するとかそういうことはありませんでした。
ものを作る姿勢なり理論なり、いろんな話や教えを受けているうちに、「ああ、この道で間違いないな」と自然に思うようになった気がします。
子供のときから工作というか、「何かを作る」ということは、上手下手とは別にして、そういうことに没頭するのは好きでしたので、ぼんやりと「そういう仕事をするんだろうな」と思ってはいましたけどね。
――I>
具体的に勉強をはじめられたのは二十歳頃からということでしたが…
――S>
初めて共同窯に研修にいったのは、二十歳頃でした。その前から絵画の勉強をしていて、まあ家業が焼き物ということでしたので、絵画ではなくてこの道に、ということになりましたが。
でも私としては絵画とかデッサンの勉強は必要や、と思ってたので、その方面にいく勉強はしたんですけれど…まあ、学校の形としてはその入試には失敗してしまいまして(苦笑)
それで絵画のほうは諦めたんですが、その後陶器をやりながら、作品の形に対するデッサンとかは続けていました。その辺がものづくりをする上の基礎になっているとは思います。
――I>
お父様からの影響を感じるところなどはおありですか?
――S>
精神的なもので言うと、「ものをつくる」ことへの姿勢の部分ではかなり大きく影響を受けていると思います。
また初代、僕の祖父もいるんですが、こちらに直接は会えてないんですよ。僕が生まれた時にはもう亡くなっていましたから。ただ、作品であるとか話で祖父の生き方やものをつくる姿勢は聞いていました。これも影響はしていると思います。
それは時代背景によってですけれどね、今このものづくりのかたちがあるのも、祖父の時代の流れがあってのもので…それは京焼の元になるようなかたちですね。色々なものをつくる、という京焼独特のかたちが祖父が京都に来たときに築かれていったのでしょう。
ちょうど、中国とかの作品を手本にして「写す」ことが全盛だったころ、競争がとても激しかった時代に、祖父は京都で焼き物をしていました。その「ものを写す」ということが勉強になるという部分で、大変影響は受けていると思います。それにそのときのこだわり方が…時代によって「写し方」が違うんですけど、当時はかなり強烈にこだわって写そうとする時代やったので、ものすごく研究もしたでしょう。どんなことにこだわって作っていたか、その姿勢は今私がものをつくる中にも影響しているところがあると思いますね。
――I>
ご自身の作品、または「澤村陶哉」のネームブランドの作品の特徴を教えてください。
――S>
初代の流れを影響、意識しながら、それとは違う意識を持って作品を作った父、という流れがあって、その両方の特徴を何とか自分の中に取り入れながら、というのがあるのですが…まだその途中の段階ですね。その中にまた「三代目」として、私自身の持っている何かをそこにプラスしていこうとなると、なかなかたどり着けるものでもないのでね。だから、特徴というと、継承することだけでも大変なことであり、それをしながら自分の表現を織り交ぜるということは、まだまだ自分のものとしては固まらないですね。
ただ、京都の「分業」で成り立っているものづくりの形の中では、それはもちろん守らないかんところですけれど…でも「分業」ではなく…厳密に言うと全く「分業」せずには焼けないんですけれど、作るところから焼きあげるまで他人の手をかけずに仕上げるという部分も、自分のこだわりにはありますね。先代の父や初代のときには殆どが「分業」、プロデュースするという形が多かったんですけれども、違いというか新しく自分のものを流れに組み入れるには、その部分がウェイトとしては少しずつ多くはなってきているかな、と思います。




あえて今、登り窯で。自ら窯を築いたそのこだわり。




――I>
分業制のころといえば殆どが共同の登り窯で焼き物をしていたと思うのですが、先生は登り窯が禁止・廃された後も登り窯での作品作りに非常にこだわっていらっしゃいますよね。
――S>
初代の時代もそうですし、先代、さらにそれ以前のもの、あるいは中国のものも、焼かれていた環境は登り窯や薪の窯であったわけです。そこからできてきた作品を皆手本としてきているので、そこに近づきたい、そのために薪や大きな窯で焼くことにどうしてもこだわってしまっていますね。
もちろん、それまで皆で共同で、分業でやっていたものを一人でやる、となるとものすごく負担が大きいんですけれども(苦笑)それでも登り窯でやろうとしたのは、この思いが強かったからだと思うんです。
――I>
それでご自身で登り窯をお作りになったんですね。
――S>
窯を作ること自体は五条のところで経験していたんですけれど、それもわーっと総勢二、三十人で作っていたのを今度は一個人、せいぜい五、六人の人手で窯を全部一からレンガを積み上げて作るとなると、やはり大変でしたね。
でも窯作りの経験はあったので、積んでいって形になる、というのは見てきてましたし、手伝ってもらいながら…まあ一年かかってひとつを作りました。所謂土木作業でしたね。その後出来上がってものが焼けるくらいになると、今度はまず道具類を集めな。京焼はむき出しで焼くわけにはいかないのが殆どなんです。薪の灰が被らんように「さや」(陶器にかぶせる陶製のケース)に入れないといけない。他の地域では、灰がかかった状態で焼いてもそれもひとつの味や、っていう焼き物もあるけど。でもその道具も窯がつぶれたときに一緒に壊してしもたんで、それを集めなあきませんでした。それに割り木。昔は薪を割る専門職の人が各地区に一人か二人いて、毎日割り木を作っていた。また窯を焼くだけの職人が四人一組で何組か。そういう人がいたから、各家は窯に作品を詰めるだけで済んでいたんです。
でもそんな人もいないから、そこも自分たちでやって…
薪の木も重要で、赤松の木じゃないとだめなんです。でも今じゃ林業も後継者がないさかいにそれも心配せなあかんし…
あとかまどの口も大きいので、大きい生木のかたまりでもらってきて、それを自分たちで割って、隙間に気をつけてしきつめるんです。でもかたまりだと木は乾きにくいから燃えへん。切るタイミングによっても乾き方が変わってしまうんです。これを見極めるのもプロのわざと言うやつで…重い生木の原木をチェーンソーで切って、割り機で割っていくんですけど、タイミングを無視して切ったらあっという間にカビたみたいになっちゃって…
――I>
窯自体だけでなくて焼くための道具や木から…本当に根本から始められたんですね。一から、というよりももうほぼゼロから…窯が潰されたことで、色々な専門職の方も皆いなくなってしまって、作家自身が全ての作業をしなければならなくなったのですね。
――S>
そうですね。小ぶりの窯を持っていた人は、五条から離れていろんなところに作ったりはしていたみたいなんですが、それも何人かいないとなかなか維持ができないので、廃れてしまっていたんです。
私の作った窯は大きさとしては…河井寛次郎記念館にあるものとほぼ同じくらいです。作品を入れる部屋が五、つあって。それにものを詰めるとなると気が遠くなるほどの量になってしまうので、そのうち三つないし四つを使う形で今はやっています。
でもあのくらいの規模がないと、染付や綺麗な白磁、青磁といったものは焼きにくい。先代は焼けない、とはいいませんでしたけど、焼きにくくていいものができないから、最低限このくらいの大きさが要る、という説明をしてくれたのでそれに倣って大きさは決めました。大きければ大きいほど守りが大変になってくるんですがね。一回に入る量も多いですし、馬力も全然違いますし、人数も必ず窯の両サイドに人がいて火を焚かないとあかんし…
――I>
窯に一度火を入れると、焼きあがるまで火が落とせないので不眠不休で見ていなければなりませんものね。
――S>
二日ほどですけどね。昔、分業制でプロがやっていたころでも、一番上の終わりにいくまで不眠不休で見ているのはとても体が持たないので、交代でやっていたんです。それも全部自分たちでやらなあかんとなると…終わった頃には相当消耗しますけどね(苦笑)
――I>
それは大変としかいいようがありませんね…年にどのくらい窯には火を入れられるんですか?
――S>
今は年に二回焼いていますね。それと京都にはなかったものですけど滋賀の信楽や伊賀とかで使われてた「穴窯」というのも一緒にやっています。最初は京都の瑞穂町だったんですが、今は滋賀の日野というところで。
最初の窯はちょうど国道から見えるところにあったせいで、煙が出てるのを見た人が火事やと勘違いして通報してしまったこともありましたね(笑)
――I>
でも実際に稼動している登り窯はなかなか見る機会も少ないものですし、一度実際に作られているところを拝見してみたいものです。
しかしそれだけしんどい思いをしても、やはり登り窯にこだわられたのには、使命感のようなものもおありだったのでしょうか。文化を護らなければ、とか自分がやらなければといったような…
――S>
そこまでの強い使命感、というたいそうなものではないですけれど、わずか50年前には登り窯しかなくて、皆それで焼いていたわけです。だから、「それで焼くのが当たり前や」って意識があるんです。確かにしんどいんですけど、特別なことをしているという気はないんですよ。それに昔の人にそんな話をしても「そんなの特別でもなんでもない」と言われてしまうのがオチでしょうしね(笑)
――I>
でもそれが一般の目から見ると、特別なこと、すごいことに感じるんですよね。受け継いだものを消さずに守る、そのお気持ちはとても大きな意味があるんだと思います。